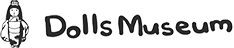こけし


こけしは、東北地方を中心に受け継がれてきた木製の伝統的な人形です。木工職人である木地師(きじし)がろくろを使って一体ずつ手作りするこけしは、地域の暮らしや信仰と深く結びついてきました。
もともとは、山の神とつながり、五穀豊穣を願う縁起物として作られたと考えられています。また、子どもの健やかな成長を願う「魔除け」としての意味もあり、農村では子どもへの素朴なおもちゃとして親しまれてきました。特に東北の温泉地では、お土産としても人気を集め、やがて全国にその存在が知られるようになります。
歴史は意外にもそれほど古くなく、江戸時代後期に始まったとされています。現在では「伝統こけし」と呼ばれる11の系統があり、各地域ごとに表情や形、模様、色使いが異なります。たとえば、宮城県の遠刈田(とおがった)系こけしは、頭に描かれた赤い髪飾り「手 柄(てがら)」や、胴に咲く菊・梅・桜の模様が特徴です。一方、福島県の土湯(つちゆ)系こけしは、頭に蛇の目模様、胴にろくろ線、比較的小さな頭部と細長い胴体が印象的です。
また、構造にも違いがあり、鳴子系に見られる「はめ込み式」は、首が回り、動かすと「キイキイ」と音が鳴ります。作並系は「差し込み式」で、首と胴体がしっかりと固定されています。秋田県の木地山系では、一本の木から削り出す「作りつけ式」が見られます。
このように、こけしは日本の民俗文化と職人技を今に伝える貴重な存在です。当館では、地域ごとの個性豊かなこけしを展示しています。