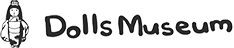五彩元禄踊


「五彩元禄踊」は、初代諏訪蘇山によって制作された作品です。五彩とは、白磁を高温で焼き上げた後、上絵具で彩色し、再び窯に入れて焼き付ける技法を指します。鮮やかな発色と華やかな意匠が特徴で、日本陶芸の美を象徴するもののひとつです。
作品の題材となっている「元禄踊り」は、江戸時代に歌舞伎音楽として成立した長唄の中でも特に有名な一曲で、元禄期(1688~1704)に上野の花見を舞台とし、武士や町人をはじめとするあらゆる階層の人々が集い、踊りに興じる絢爛豪華な情景を描いています。その華やぎを陶器の造形に移し替えたこの作品には、時代の活気と人々の喜びが色濃く表れています。
作者である初代諏訪蘇山は加賀国金沢(現在の石川県金沢市)に旧加賀藩士の家系で生まれた陶芸家で、明治から大正にかけて活躍しました。国内外での研究や創作活動に尽力し、1917年には宮内省より帝室技芸員に任命されるなど、その功績は高く評価されています。当館所蔵の「五彩元禄踊」もまた、その卓越した技と芸術性を今に伝える貴重な作品です。