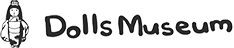五月人形


五月人形とは5月5日の「端午の節句」に男の子の健やかな成長や幸運を願って飾られる縁起物として知られています。しかし、実はこの日はもともと「忌み日」、つまり縁起の悪い日と考えられていました。
端午の節句の起源は奈良時代に大陸から伝わった風習にさかのぼります。当時の宮中では、邪気を払うために魔除けの植物とされていた菖蒲(しょうぶ)を使って宮殿を飾り、天皇が家臣たちと共に馬の競争や弓の演武を鑑賞する儀式が行われていました。その後、平和な江戸時代に入ると、植物の「菖蒲(しょうぶ)」が「勝負(しょうぶ)」という言葉にかけられ、端午の節句は男の子の誕生や成長を祝うめでたい日へと変化していきました。このような背景から、五月人形には歴史上の武将や英雄など、強さや勇気を象徴する人物が多く登場します。
当館では義経や弁慶など、江戸時代から大正時代にかけて作られた五月人形を展示しています。