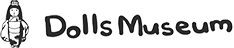享保雛 (きょうほびな)


享保雛は江戸時代の享保年間(1716〜1736年)に流行した雛人形の様式です。
この時代の将軍が徳川吉宗であったため、その治世の名である享保という名前がつけられています。
享保雛の特徴は、面長の顔立ち、切れ長の目、そして能面を思わせる静かな表情にあります。簡素ながらも上品で気品のあるその姿は多くの人々に愛され、今日まで大切に受け継がれてきました。
雛人形
ひな人形は女の子の健やかな成長と幸せを願って、3月3日の雛祭りに飾られる伝統的な人形です。関西では豪華な衣装をまとった天皇・皇后を表す御殿飾り、関東では宮中の様子を再現した段飾りなど、その種類や飾り方は多様です。
このような美しい風習は、意外にも古代から続くものではなく、江戸時代に入ってから現在のような形が整えられました。もともとは、紙の人形を川に流して厄を払う「流し雛」の風習がありましたが、次第に人形を飾って祈る行事へと発展していったのです。