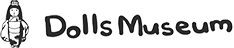土人形


土人形は日本各地に伝わる素焼きの人形で、素朴であたたかみのある風合いが特徴です。その起源は京都・伏見で作られた伏見人形とされており、江戸時代になると、北前船と呼ばれる商船の流通を通じて、各地に技法や意匠が広がっていきました。
その土地の風土や信仰、暮らしの中から生まれた土人形は、地域ごとに個性豊かな表情や形を持ち、まさに地元の文化を映し出す存在です。もともと上流階級向けに作られていた高級な人形とは異なり、土人形は庶民の日常に根ざしたもので、願いを込めた縁起物や、子どもたちへの素朴なおもちゃとして親しまれてきました。
現代では、かつてのような玩具や信仰の対象としての役割は薄れ、地元の民芸品や観光土産としての側面が強くなっています。しかしその一方で、ユーモラスで温かみのある造形や、民話・風刺・教訓を含んだモチーフに改めて注目が集まり、静かな人気の高まりを見せています。
ただし、作り手の高齢化や後継者不足により、土人形の製作をやむなく中止する地域も増えているのが現状です。土地ごとの精神や文化が込められた土人形は、今こそ大切に守り伝えるべき日本の貴重な民俗文化だといえるでしょう。
当館では、日本全国の土人形を日本地図に沿って展示し、それぞれの特徴をご紹介しています。