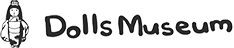有職立ち雛 (ゆうそくたちびな)


有職立ち雛とは平安時代の貴族の装束や髪型、礼式を忠実に再現した立ち姿の雛人形です。「有職」とは、朝廷や貴族社会で用いられていた儀式や服飾に関する伝統的な知識や形式のことを指し、それに基づいた意匠がこの人形の名前の由来となっています。
立ち雛は雛人形の最も古い形とされ、江戸時代の前期から作られてきました。多くの場合、美しく彩色された厚紙で胴体を作り、頭部を別に作って差し込むという、簡素ながら洗練された構造を持っています。有職立ち雛はその中でも特に格式高い様式であり、衣裳の織りや模様、色づかいに至るまで、細部にわたって当時の貴族の衣装を忠実に再現しています。
雛人形
ひな人形は女の子の健やかな成長と幸せを願って、3月3日の雛祭りに飾られる伝統的な人形です。関西では豪華な衣装をまとった天皇・皇后を表す御殿飾り、関東では宮中の様子を再現した段飾りなど、その種類や飾り方は多様です。
このような美しい風習は、意外にも古代から続くものではなく、江戸時代に入ってから現在のような形が整えられました。もともとは、紙の人形を川に流して厄を払う「流し雛」の風習がありましたが、次第に人形を飾って祈る行事へと発展していったのです。