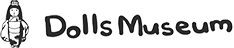十二代沈壽官 母子像(薩摩焼)




「母子像」は、輸出工芸品「ハマモノ」のひとつで、薩摩焼を代表する名工・十二代沈壽官による作品です。薩摩焼の起源は400年以上前、文禄・慶長の役(1592・1598年)にまでさかのぼります。朝鮮出兵ののち、薩摩藩主・島津義弘が連れ帰った朝鮮陶工によって始められ、以後、江戸時代を通じて藩の重要な産業として保護されてきました。
その名が広く知られるようになったのは幕末の慶応3年(1867)、日本が初めて参加したパリ万博でした。薩摩焼は異国の地で高い人気を博し、さらに明治6年(1873)のウィーン万博では十二代沈壽官が大きな賞賛を受けました。その後、ジャポニスムの流行に後押しされ、薩摩焼は欧米で熱狂的に受け入れられ、一世を風靡する存在となります。
明治26年(1893)のシカゴ万博において、十二代沈壽官は従来の薩摩焼では難しかった大胆な造形表現=「捻り物」を発表しました。本作「錦手母子像」もまた、その時代に確立された技法によって制作されたもので、明治20年代の作品と考えられています。母子を主題としたこの像は、繊細な彩色と柔らかな造形によって、当時の薩摩焼が持つ芸術性と国際的な広がりを物語る貴重な一品です。