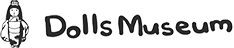藪明山-織姫彦星像


こちらの織姫彦星像は19世紀の薩摩焼を代表する名工・藪明山(やぶめいざん)によって作成されました。 世界的にも貴重とされる「捻り物 (置物細工の薩摩風の呼び方) 」の作例のひとつで、白磁部分は鹿児島の名窯・12代沈壽官窯によって成形され、そこに藪明山が繊細な上絵付けを施しています。
藪明山は、薩摩焼の中でも特に高く評価された工房であり、大阪薩摩とも称され、19世紀後半の欧米で巻き起こったジャポニスムの潮流の中で重要な役割を果たしました。その作品はヨーロッパやアメリカに向けて輸出され、万国博覧会などでも高い評価を受けました。この織姫彦星像は米国・ビバリーヒルズに所蔵されていたものが2024年春に日本へ奇跡的に里帰りしたものです。
人形の成形を担当したと考えられる染浦泰京(そめうら たいきょう)は、12代沈壽官窯に仕えた形成師であると同時に、薩摩焼の産地・苗代川にある玉山宮(現在の玉山神社)の神官も務めていました。深い信仰心をもって生きた工人だからこそ、宇宙的な広がりと霊的な気配を湛えた本作を生み出すことができたのでしょう。
「織姫と彦星」は、年に一度だけ天の川を越えて再会できるという、日本の七夕伝説に登場する恋人同士です。 本作は、その切なくも力強い愛の象徴として、まさに「見て感じる」芸術作品です。